はじめに
江戸時代後期、伊能忠敬の作成した「大日本沿海輿地全図」は、日本列島を正確示した地図で、幕府も国防の観点から地図の持ち出しを禁じていた。しかし、長崎に来日していたオランダ人医師シーボルトが、国外持ち出し禁止した「大日本沿海輿地全図」を手に入れて、国外に持ち出そうとした事件が起こった。シーボルトはどのようにして地図を手に入れて、国外に持ち出そうとしたのか?詳しく見てみましょう。
シーボルトの来日
事件が起きる5年前の1823年(文政6年)8月にシーボルトは日本に来日しました。来日したシーボルトは長崎の出島のオランダ商館医になった。当時のオランダ商館長はヨハネス・テンデンスでした。
シーボルトは本来はドイツ人であり、シーボルトが話すオランダ語は、日本人通訳士よりも発音が不正確であり、通訳士に怪しまれたが、「自分はオランダ山地出身の高地オランダ人なので訛がある」「山オランダ人」と偽って、(その場を切り抜けた。オランダはその名の通りネーデルラント(低地地方)と呼ばれているので、国土のほとんどが干拓地であって山地は存在しない)そのような事情を知らない日本人にはこの言い訳で通用した。または、オランダ語は系統的に低地ドイツ語の一種と見なされており、高地ドイツをこれに対する地域として表現したともいえる。シーボルトとエンゲルベルト・ケンぺルとカール・ペーテル・ツンベルク合わせた3人を「出島三学者」などと呼ぶことがあるが、全員オランダ人ではなかった。
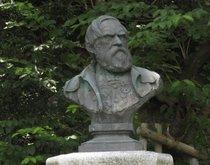
鳴滝塾を開業
シーボルトは出島内において開業の後、1824年(文政7年)には出島の外で鳴滝塾を開設しました。鳴滝塾は西洋医学(蘭学)教育を行う塾で、日本各地から集まってきた多くの医者や学者が学びました。その塾生で代表が高野長英・二宮啓作・伊東玄朴・小関三英・伊藤圭介らがいました。門下生は卒業後医者・学者として活動しています。シーボルトは日本文化の探求や研究をしたり、長崎の町で特別に診察することを許された。
翌1825年(文政8年)出島内に植物園を作り、日本を退去するまでに1400種以上を栽培した。

シーボルトの江戸参府
1826年(文政9年)4月には162回目にあたるオランダ商館長(カピタン)ステューレルが江戸参府が決まり。シーボルトもこれに随行しました。シーボルトは道中を利用して日本の自然を研究することに没頭し、地理や植生、気候や天文などを調査した。
またシーボルトは、江戸滞在にした時、商館長と共に葛飾北斎と面会しました。肉筆画などを直接注文したとされる。シーボルトはステューレルと共に江戸城で将軍徳川家斉に謁見した。その後、江戸にでたくさんの学者らと交友しました。将軍御典医桂川甫賢・蘭学者宇田川榕庵・薩摩藩主島津重豪・重豪の嫡子で、奥平家に養子に入った中津藩主奥平昌高・蝦夷探検家最上徳内・天文方高橋景保らと交友した。この年、それまでに収集した博物標本6箱をライデン博物館へ送る。
シーボルトは最上徳内からは北方の地図を貸りた。高橋景保がクルーゼンシュテルンによる航海記『世界周航記』に関心を持ったことから、景保の「大日本沿海輿地全図」の写しとシーボルトの『世界周航記』の交換が成立した。
楠本滝との結婚
シーボルトは日本に来日した直後に、長崎で遊女をやっていた楠本滝(源氏名其扇)と出会って、結婚した。1827年には娘イネ(楠本イネ)を生んだ。また、シーボルトは日本で見つけたアジサイに「ヒドランゲア・オタクサ」と名付けました。「オタクサ」とはシーボルトが滝を呼ぶときの名です。

シーボルト事件
シーボルト事件の発覚
シーボルト事件の発端は、シーボルトが江戸に参府した時に高橋景保から「大日本沿海輿地全図」の写しを貰った時に始まる。シーボルトらが、1826年7月に江戸から出島に帰還した。シーボルトはこの旅行の間にも1000点を超える日本名・漢字名植物標本を収集していたが、さらに日本の北方の植物にも興味を抱き、間宮林蔵が蝦夷地で採集した押し葉標本を手に入れるためにシーボルトは間宮林蔵に書簡と布地を送った。しかし、間宮は外国人との私的な物品の贈答は日本の国禁に触れると考え、書簡を開封せず上司に提出した。
間宮の提出した書簡が発端となり、高橋景保をはじめ多数の関係者が幕府の取り調べを受けた。この裏には間宮林蔵と高橋景保との間には確執があったといわれる。また、この当時、事件が発覚したのは間宮が告発を行ったためであると信じられていた。
シーボルト事件の経過と処分
江戸で高橋景保が逮捕されると、幕府は景保がシーボルトに送った「大日本沿海輿地全図」の写しを押収するよう長崎奉行所に内命を下し、出島のシーボルトは長崎奉行から尋問と家宅捜索を受けた。軟禁下のシーボルトは研究活動と植物標本や剥製の作製を行って過ごした。このときのシーボルトは大量の動植物の標本や個人的に収集していた絵画などを無事にオランダやバタヴィア(インドネシアの首都ジャカルタのオランダ植民地時の名称)に搬出できるか懸念していた。伊能忠敬作の「大日本沿海輿地全図」の写しなど禁制品は押収されました。『北斎漫画』などの絵画の類はバタヴィア経由でオランダのライデンへ送られている。
シーボルトは幕府の尋問に対し、自分の情報収集はもっぱら学問上の目的によるものであると主張し、「大日本沿海輿地全図」の写しの返還を拒否した。また、捕まった日本の高橋景保ら友人らを助けるため彼らに責任があることを否定し、さらにみずから日本の住民となって終生日本に留まることで人質になることを申し出ました。しかし、1829年(文政12年)3月に友人の高橋景保が獄死しました。景保の死により、シーボルトの身も危ぶまれたが、彼の陳述によって多くの友人や協力者が助かったといわれる。しかし、「大日本沿海輿地全図」の写しなどの日本地図の国外持ち出し禁止を知らなかったとは考えにくいこと、日本近海の海底の深度測定を行っていたことなどから、幕府はシーボルトに対するスパイの疑いを解かず、「大日本沿海輿地全図」の写しを没収の上に国外追放。シーボルトの日本への再渡航禁止の処分とした。
日本側関係者の処分は多岐にわたった。シーボルトに「大日本沿海輿地全図」の写しを贈った高橋景保は獄死したが、その死体は塩蔵され、のちに改めて死罪判決が下されたうえで斬首された。また、景保の子らも遠島となった。ベラドンナ(実際にはその代用品であるハシリドコロ)を用いた開瞳術を教わる見返りとして将軍家斉から拝領した三つ葉葵の紋服を贈った眼科奥医師土生玄碩は改易のうえ終身禁固となった(のち赦免)。その他、オランダ商館長が江戸に参府する際の定宿を提供していた長崎屋源右衛門・シーボルトの門人二宮敬作・高良斎・出島絵師川原登与助(川原慶賀)、通詞の馬場為八郎、吉雄忠次郎、稲部市五郎、堀儀左衛門、末永甚左衛門、岩瀬弥右衛門、同弥七郎、さらに召し使いにいたるまで五十数人が処罰された。

シーボルト事件後のシーボルト
1829年(文政12年)10月にシーボルトは出国した。景保がシーボルトに贈った伊能忠敬の「大日本沿海輿地全図」の写しは没収されたとされているものの、シーボルトはひそかに同図を持ち出しており、1840年にはオランダで伊能図にもとづく日本地図が発行された。
シーボルト事件から30年後の1858年(安政5年)に日蘭修好通商条約が締結されると、シーボルトの再渡航禁止処分も解除された。翌1859年、シーボルトは長男アレクサンダーを伴って再来日し、幕府の外交顧問となった。この2度目の来日中の1862年(文久2年)にも、シーボルトのために日本の歴史書を翻訳したかどで、秘書役の三瀬諸淵が捕らえられるという事件が起こった。ただし、諸淵の妻でありシーボルトの孫娘にあたる楠本高子(シーボルトが国外退去となった時。2歳だった娘楠本イネの子)の手記は、諸淵が捕らえられた理由を歴史書の翻訳とはしていない。
シーボルト事件の原因
シーボルト事件の件が発覚した原因に関しては、シーボルトが入手した禁制品を載せた船が暴風雨(シーボルト台風)に見舞われて座礁し、積み荷から地図などが発見されたことによって露見したとする蘭船積み荷発覚説が、従来の一般的だった。1996年に梶輝行氏が暴風雨で座礁した船内から地図などの禁制品が発見されたという逸話が後世の創作であることを明らかにして以来、江戸露見説が有力である。
シーボルト事件当時の『オランダ商館長の日記』によると、問題の地図を積んでいたとされるコルネリウス・デ・ハウトマン号は1828年10月に出航を予定していたが、同年9月17日夜半から18日未明に西日本を襲った猛烈な台風(シーボルト台風)のため座礁し、同年12月まで離礁できなかった。船に積み込まれていたのは船体の安定を保つためのバラスト用の銅500ピコルだけであり、座礁した船は臨検されることなくそのままにされた。また、2019年には、長崎で三井維越後屋の代理店を経営していた長崎商人中野用助が江戸の本店に送った事件の報告書の写しが発見された。中野の報告書では、事件の経緯について、まずシーボルトの伊能図所持が江戸で発覚し、江戸から飛脚で長崎に通報され、それを受けて長崎奉行所がシーボルトを取り調べた結果、伊能図をはじめさまざまな禁制品が見つかったとされており、この内容は『オランダ商館長の日記』を裏付けるものとなっていた。




コメント